| 綺羅めく京の明治美術 |
|
|
綺羅めく京の明治美術
京都市京セラ美術館 2022.7.23-9.19
皇室によって美術工芸家を顕彰、保護を目的とした1890(明治23)年発足した帝室技芸員制度。
技芸員は、いわゆる御物や、正倉院の宝物を特別に鑑賞できたり、毎年100円を貰える特例がありましたが、品格等様々な厳しい審査があり、当初は上限20名(後に25名)という枠がありました。
今回の展覧会では、京都にゆかりのあった19名を紹介しています。
幕末は長州藩お抱え絵師で、京都と長州を往復し情報収集等政治活動も行っていたと言われる森寛斎(1814-94)の女性の姿をした梅の精を描いた≪羅浮仙人図≫(1888)、秋風に吹き破られた蓮を描いた幸野楳嶺(1844-95)の≪敗荷鴛鴦図≫(明治10~20年代)、三菱財閥の岩崎弥之助からの注文で、右隻に李白の詩『春夜宴桃季園序』、左隻に司馬光の『独楽園記』を絵画化した川端玉章(1842-1913)の≪桃季園独楽園図屏風≫(1895)、ジャガード機を西陣織に取り入れた五世伊達弥助(1838-92)が岸駒の絵を元に作成し、没後シカゴ・コロンバス世界博覧会に出品・優秀書を獲得した≪錦地百蝶図壁掛≫(1892)他。
副題は、「世界が驚いた帝室技芸員の神業」。
https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20220723-20220919
| |
|
9月17日(土)20:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 関西美術センター | 管理
|
| 清水九兵衞/六兵衞 |
|
|
清水九兵衞/六兵衞
京都国立近代美術館 2022.7.30-9.25
1968(昭和43) 年それまで彫刻家としては「五東衞」と名乗っていたが「九兵衞」を名乗り、彫刻と陶芸の二つの分野を創造していった清水九兵衞/六兵衞(1922-2006)の生誕100年の初大回顧展。
1980(昭和55)年に六代目の急死により七代目清水六兵衞を襲名したが、襲名披露展は1987(昭和62)年まで開催されなかった。
その清水六兵衞の名も、2000(平成12)年に長男に譲り、彫刻と陶芸の融合に挑戦しました。
展示品は、資料、写真パネルを含め168点。
清水九兵衞の公共展示している場所のわかる学芸員作成の「京の街角てくてく久兵衞さんマップ」も受付でもらってください。
https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2022/449.html
| |
|
9月11日(日)23:01 | トラックバック(0) | コメント(0) | 関西美術センター | 管理
|
| 矢沢あい展 |
|
|
ALL TIME BEST 矢沢あい展
大阪髙島屋7階グランドホール 2022.8.24-9.12
大阪生まれで尼崎育ちの矢沢あい(1967-)の直筆原画やイラスト約300点の巡回展。
作家本人は、2009年より連載中の『NANA』を休載し、病気療養中ですが、この展覧会の総監修、イラスト等の活動で徐々に回復されているようです。
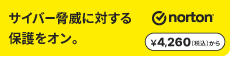 
https://yazawaai-ten.com/
| |
|
9月4日(日)15:34 | トラックバック(0) | コメント(0) | 関西美術センター | 管理
|
| 千總の屏風祭 |
|
|
千總の屏風祭
千總ギャラリー 2022.6.28-9.5
1902(明治35)7月24日、『京都日出新聞』(京都新聞の前身)に掲載された「御屏風拝見」に基づいて「屏風祭」を120年に再現されています。
五つの屛風は、山口素絢(1759-1818)の≪やすらい祭図≫(1808)、禅の修行の手引き「十牛図」の第六図「騎牛帰家」を描いた伝長澤芦雪(1754-99)の≪牧牛と童子図≫(江戸時代後期)、1731(享保16)から約2年長崎に滞在した清の画家・沈南頻(1682-?)の作と伝わる≪群鹿図≫(1725)、屏風の両端の書は中国最古の詩集『詩経』からの一説です。
中国では古くから教養のある人々の嗜みの四つを伝・北海友松(1533-1615)が描いた≪琴棋書画図≫(桃山~江戸時代初期)、岸竹堂(1826-97)は、右隻に雪景色を背景に二頭の馬、左隻に桜の蕾と牛三頭を対比させた≪牛馬図≫(1895)です。
会期は当初8月22日まででしたが、9月5日に延期されています。
https://www.chiso.co.jp/gallery/
| |
|
9月1日(木)19:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | 関西美術センター | 管理
|